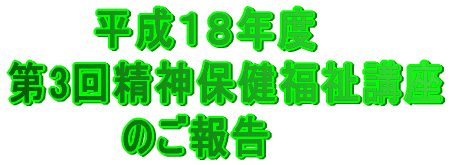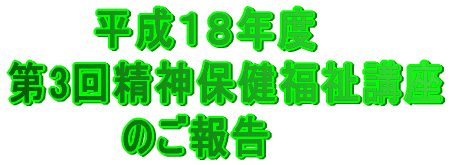| 第2回 「アルコール問題はどのように扱われてきたか」 |
2月23日は、52名の方が参加されました。
講演は、前回の内容にも触れながらアルコール依存症者は依存症であることを否認するため、医療機関への受診や回復への取り組みが遅れること、内科的疾患のみと捉え、身体的に回復したことに安心し、飲酒を再開している例もあること、またアルコール依存症は完治できないが、お酒を飲むことを止める(断酒)努力をし続けることで回復が可能であると話されました。 |

|
板書やビデオでは、家族がアルコール依存症者の世話を焼いたり、失禁の後始末や会社への休みの連絡を肩代わりする行為などが、問題を終結したいという意図とは逆に本人に依存の状態を助長してしまうこと、そのような関係状態にある人をイネイブラーといい、家族のイネイブラーからの回復が依存症者の回復に必要であるということでした。そのためには、家族が家族教室で病気について学び、依存者はARP(アルコールリハビリテーションプログラム)や断酒会などの自助組織に参加し、共に回復に取り組んでいくことの重要性など、依存症者と家族との関わり方について説明されました。
質疑応答では、口頭や記入で寄せられた多くの質問に時間が足りなくなるほどでした。アルコール依存症から回復され、現在は自助組織や啓発などの活動をされている方からもお話をしていただきました。 |